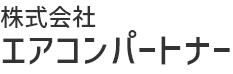暖房が効かない?エアコン暖房効率が落ちる原因を「工事目線」で徹底解説
暖房クレームは「エアコンのせい」だけではない
冬場の現場でよくあるのが、「暖房が効かない」「設定温度までなかなか上がらない」という問い合わせです。お客様からすると、「新品のエアコンなのにおかしい」「他の部屋より寒い」と感じてしまうので、どうしても機器不良や工事不良を疑われがちです。
ただ、実際に現場を見ている職人であれば分かる通り、暖房効率が落ちる原因は「本体の性能」だけではありません。設置環境、配管ルート、室外機の置き方、配管断熱の処理、そもそもの容量選定の時点で負けているケースなど、工事側が関われるポイントがかなり多いです。
ここでは、エアコン工事業者の視点から「暖房効率が落ちる典型的な原因」と「工事でコントロールできる部分」「幹事会社や工事センターと組むことで減らせるトラブル」について、できるだけ具体的に整理していきます。
室内機の設置位置が原因で暖房が届かないパターン
まず工事目線で真っ先に疑いたいのが、室内機の設置位置です。冷房に比べて暖房は「足元まで暖気をどれだけ落とせるか」が快適性に直結しますが、設置位置を間違えると暖気が天井付近に溜まり、床付近はいつまでも寒いという状況になりやすくなります。
よくあるのは、梁やカーテンレールのすぐ上ギリギリに付けてしまい、吹き出しの風がすぐ天井に当たってしまうパターンです。この場合、エアコン自体はしっかり能力を出していても、暖かい空気が部屋全体に回らず、お客様は「効きが悪い」と感じてしまいます。
他にも、部屋の長手方向を無視して短い辺に向かって風を出していると、奥のスペースに暖気が届かず、これも体感としての「暖まりにくい」原因になります。本当は長手方向に風を飛ばして、サーキュレーションを意識したいところですが、筋交いや下地位置の制約でどうしても厳しい場面もあります。
こういった現場では、工事時点で「暖房を意識した設置位置」をどこまで提案できるかが職人の腕の見せ所です。お客様に一言「暖房重視ならこちらの位置の方が効きが良いですよ」と説明できるかどうかで、クレームリスクも評価も大きく変わります。
室外機の設置環境が暖房効率を大きく左右する
暖房効率に関しては、室外機の置き方もかなり重要です。暖房運転時、室外機は外気から熱を回収して室内に送り込んでいるため、外気温が低いほど負荷が大きくなります。そこに「悪条件」が重なると、一気にパフォーマンスが落ちます。
よくあるのは、北側の路地で風が強く当たる場所や、ビル風が直撃するような位置です。強風が常に当たると熱交換器から熱を奪われやすくなり、暖房能力が落ちるだけでなく、着霜や除霜の回数も増えます。結果として、お客様は「暖房がすぐ止まる」「ぬるい風ばかり出る」と感じてしまいます。
また、積雪地域やベランダ置きの場合は、室外機周りの空気が滞留したり、雪で吸い込み・吹き出しが塞がれたりするリスクもあります。積雪を考慮せずに地べた直置きにしてしまうと、一晩で吹き出し口が雪に埋まり、暖房能力がガタ落ちするケースもあります。本来であれば架台の高さを確保したり、事前に寒冷地仕様を提案したりするのがベストです。
工事業者としては、単に「置ける場所」ではなく、「暖房にとって有利な場所はどこか」という視点で設置位置を考えることが重要です。もし条件が悪い場合には、工事前の写真段階で幹事会社に相談し、現場説明や追加部材の提案をしておくことで、後からのクレームややり直しを減らすことができます。
配管ルートと断熱処理の差が、冬場に露骨に出る
暖房効率に大きく影響するもうひとつの要素が、冷媒配管の取り回しと断熱処理です。特に暖房時はガス管側が高温になるため、断熱が甘いとそこで熱をロスしてしまい、室内機に届く熱量が目減りします。
例えば、配管を長く外気にさらしたままにしていたり、テープ巻きだけで終わらせてしまったりすると、冬場に一気に差が出ます。見た目だけ合わせてあっても、実際は一部の断熱材が薄かったり、途中で切れていたりするケースもあり、そうなると暖房能力のロスだけでなく、結露や腐食の原因にもなります。
また、無理な曲げやつぶれがある配管、必要以上に長い配管も、暖房効率を下げる要因です。カタログには配管長の限界値が記載されていますが、上限ギリギリまで引っ張ってしまうと実効能力はどうしても落ちます。特に暖房重視の現場では、「配管長をなるべく抑える」「曲げを少なくする」という基本がとても大事です。
ここは完全に工事側の技術領域なので、こうした細かい部分にこだわる職人ほど、冬場の「なんかこの部屋だけ効きが悪いんだよね」というクレームを減らせますし、幹事会社からも「この人に任せておけば大丈夫」と評価されやすくなります。
容量選定と建物の断熱性能のミスマッチ
実は、暖房効率の問題で一番やっかいなのが、「そもそも容量が足りていない」パターンです。特に、賃貸や中古物件でよくあるのが、冷房だけを基準に6畳用・8畳用を選んでしまい、暖房時の負荷を見落としているケースです。
北向きの部屋、大きな掃き出し窓がある部屋、天井が高いリビング、隙間風が多い築古物件などは、本来は一つ上の容量を選びたいところですが、価格重視で小さめの機種が入ってしまうことも少なくありません。こういった条件では、どれだけ工事を丁寧にしても、真冬の朝一番などには「なかなか暖まらない」と感じられてしまいます。
工事業者としてできることは、現場を見た段階で「この部屋条件だと、暖房は少し弱いかもしれません」と一言伝えられるかどうかです。幹事会社によっては、事前の現調写真や間取り情報を共有してくれるところもあり、そこで容量や寒冷地仕様を一緒に検討してくれるケースもあります。こうした会社と組めると、そもそも「暖房効かないクレーム」が出にくい現場づくりができるようになります。
メンテナンス不足が“工事クレーム”に飛んでくることもある
暖房効率が落ちる要因として、お客様側のメンテナンス不足も無視できません。フィルターの目詰まり、熱交換器の汚れ、室外機周りのゴミや落ち葉、室外機の前に物を置いてしまっているケースなど、実際に現場でよく見る光景です。
ただ、これも工事時点の説明次第で、かなり防げる部分があります。取り付け完了後に「暖房をしっかり効かせるためには、フィルター清掃をこのくらいの頻度でお願いしたいです」「室外機の前には物を置かないようにしてください」と一言添えるだけでも、後の印象は変わります。
丁寧な工事と、ちょっとした説明。このセットができる職人は、お客様からも幹事会社からも信頼されやすく、その結果として「指名」や「担当指定」をもらいやすくなります。同じエアコン工事という仕事でも、こうした積み重ねで売り上げが大きく変わっていくのが面白いところです。
まとめ:暖房効率を理解している職人は、冬に強い
暖房効率が落ちる原因は、室内機の位置、室外機の環境、配管の取り回しと断熱、容量選定、建物の断熱性能、メンテナンス状況など、実にさまざまです。そして、その多くは工事業者の工夫や事前の一言説明で、ある程度コントロールすることができます。
エアコン工事という仕事は、単に「付けて終わり」ではなく、冷暖房の仕組みを理解し、現場ごとの条件を読み解きながらベストな形を作っていく“技術職”です。特に暖房は、お客様の生活の「快適さ」と直結しているので、ここにこだわりを持てる職人は、冬でもしっかり稼げる人材になっていきます。
私たちにとってエアコン業者様は、なくてはならない大切なパートナーです。
事業を拡大し、成長し続けるためには、弊社の努力だけでは足りません。
協力業者様と連携・協力ができて初めて、業績を伸ばしていけるのです。
協力業者様とお客様、お取引先様、弊社、全員がプラスになるような、Win-Winの関係性を最も重要視しています。
その為、弊社ではエアコン工事業者様を常に募集しております。
仕事でかかわる全員で有意義な関係を作っていきたいと思い、日々精進してまいります。
エアコン工事業者様からのご応募をお待ちしております。
TEL:052-799-7117
エントリー:https://air-conditioner-partner.com/entry/